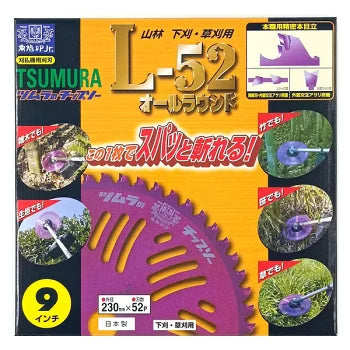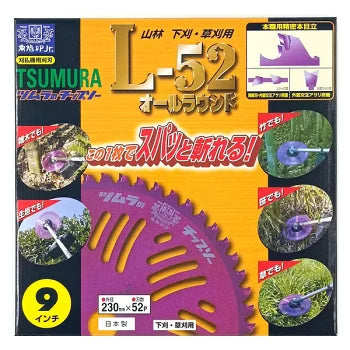今回訪れたのは、大分県宇佐市にある「宇佐ジビエファクトリー」(有限会社サンセイ)。 ”身体にやさしい”をコンセプトに、化学調味料を使わず天然素材にこだわって造り上げた「安心院(あじむ)ソーセージ」として、ソーセージやジビエ肉、その他加工肉などを取り扱っています。 宇佐ジビエファクトリーとは 「宇佐ジビエファクトリー」は、有限会社サンセイの”ジビエ加工施設”。 大分県内で捕獲されたイノシシやシカの約97%が廃棄されていることを知り、食肉加工業者としてジビエ食材を有効活用することが使命と考え立ち上げました。 捕れたての魚のようにジビエも鮮度が命。 室温4度設定という、まるで冷蔵庫のような部屋で作業をすることで、菌の繁殖を防ぎ、安全安心な肉として取り扱っています。 国内でも有数の「国産ジビエ認証施設」として、単に処理をするだけでなく、安全安心に、そして味にもこだわったジビエとして加工しています。 全国的でも数少ない、年間1000頭を超える処理施設の一つです。 ※国産ジビエ認証制度: 衛星管理基準およびカットチャートによる流通規格の遵守、適切なラベル表示によるトレーサビリティの確保等に取り組む食肉処理施設の認証を行う。 2018年5月に制定され、より安全なジビエの提供と消費者のジビエに対する安心の確保を図る制度。 ジビエを始めたきっかけ もともと焼肉店の運営などをしていた同社。当時は高級な食べ物であった焼肉を、おいしくて良いものを安心価格で食べてもらいたいと考え、無添加の加工肉を自分たちで作って提供することを決意し、2011年に「安心院ソーセージ」を設立します。 その後、ジビエ食肉加工も始めることになりますが、そのきっかけは、農家の方の「イノシシやシカの処理をどうにかできないか」との一声だったそう。 ある日、その農家の方が、野生動物に農作物を食い荒らされてしまい困っていたところを猟友会に捕獲を頼みます。しかし、猟師は役所に届けるのに必要な”しっぽ”だけを取っていき、残りはその場に捨ててしまう始末であったといいます。 「動物が腐敗していく状況を見るのがつらく、農業を辞めようかと思っている」と、そんな話を聞き、何とかしたいと思い、研究を重ねてジビエ食肉加工を始めました。 肉の仕入れについて ジビエを商材とするのにあたり無くてはならないのが、肉の仕入れです。 肉は猟友会の協力のもと、約30名の猟師に年間1,600頭ほど提供してもらっています。 そのうち、シカが8割・イノシシが2割。シカの林業被害が多いこともあり、イノシシに比べてシカの方が自治体の報奨金が高くなっていることも要因の一つと考えられます。 「宇佐ジビエファクトリー」では、畜肉を扱う肉のプロ目線と、これまで多くのジビエを取り扱うことで得た目利き力を活かして、質の良い肉を仕入れることができているといいます。 また、対象地域が限られますが、持ち込みが難しいという方には、現場に行っての引き取りも行っています。 ジビエへの思い ジビエの普及に対して、一般的にはマイナスなイメージがついているのが現状です。 血抜きや鮮度に対してあまり知識を持っていない、こだわりのない処理施設が作ったジビエは臭みが強かったり、猟師からおすそ分けでもらったジビエは、実は長い期間冷凍庫に保管されていたものも多いと聞きます。 そういった貴重な命が扱い一つでイメージダウンしてしまっていることに心を痛め、”どの命も無駄にしないこと”を使命として、受け入れたイノシシやシカを今日も大事に扱っています。 学校給食でジビエを ジビエのイメージアップの一つとして活用しているのが、”学校給食”です。 食育や郷土愛の観点から、年に2回ほど大分県内の小・中学校の給食へジビエを提供しています。 新型コロナウイルスの影響で、学校給食用に加工していたものが提供直前にキャンセルになってしまうというつらい時期もありました。 しかしその経験をきっかけに、業務用や卸だけでなく一般の方にも販売してみようと考え、オンライン販売を始めることができたといいます。 ジビエの利活用 ジビエの活用を始めたものの、地域から供給されるジビエは、半分がまずい肉であり、それらの肉の利用に苦慮したといいます。 普段の生活で食べている畜肉の牛肉や豚肉は、去勢などをすることによってオス臭のない柔らかくておいしい肉を作ることができますが、野生のイノシシやシカはそうはいきません。 人工的な管理ができないことに加え、季節的な肉質の変化もあることから、肉が硬く臭みがあって食べられないという人が多いのもそういった理由の一つだといいます。 衛生面的には問題はありませんが、食味が劣ってしまう部分に関してはペットフードやジャーキーにしています。 また同じ宇佐市安心院町にある、日本最大級のサファリパーク形式の動物園「九州自然動物公園アフリカンサファリ」に肉食獣の餌としての提供にも利用しています。 全国有数のライオンの飼育数を誇っているアフリカンサファリは安定した提供先であり、肉を無駄なく使うことができることから、「ジビエ版地産地消」として地域へ貢献することができる一つとなっています。 またコロナ禍には、農林水産省の「#元気いただきますプロジェクト」に賛同し、自社のソーセージを子供食堂に無料で提供したりと、地元だけでなく全国に向けても活動を行ったりしました。...