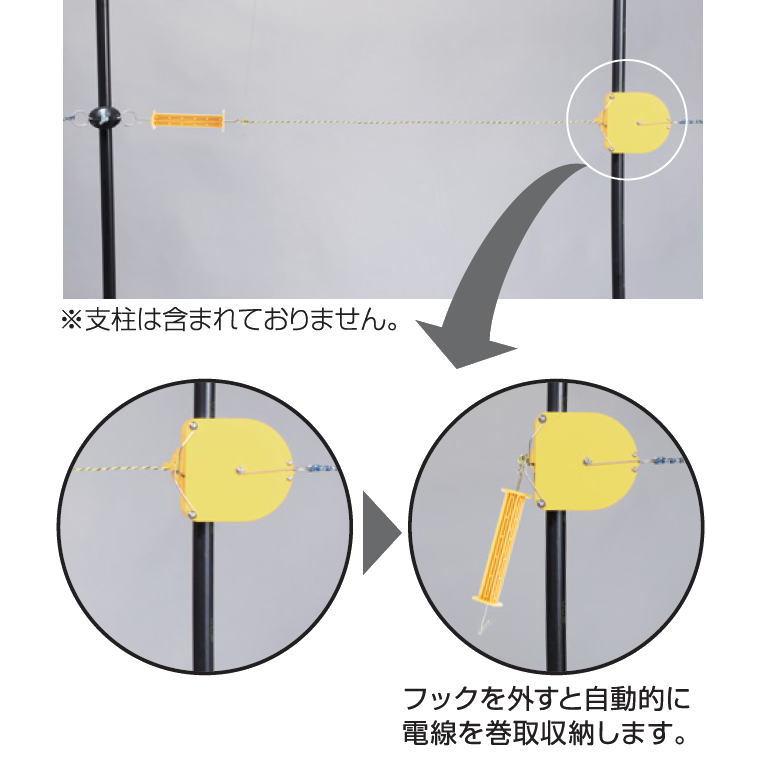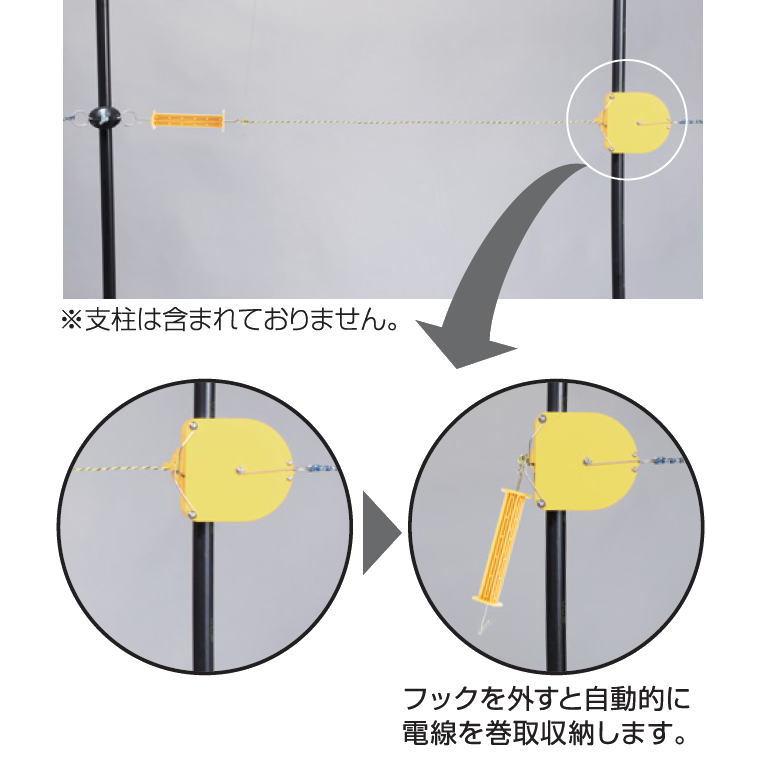電気柵は、イノシシやシカなどの害獣から畑を守る効果が期待できる製品です。しかし、電気が流れることから危険なイメージを持っている方も多いでしょう。本記事では、電気柵による事故の詳細を紹介するとともに、市販の電気柵の安全性を解説します。また、市販の柵の魅力や事故を起こさないための対策も紹介するため、設置を検討している方はぜひ参考にしてください。 目次 1電気柵による事故の事例:静岡県西伊豆町 2電気柵の役割とは 3電気柵は安全?危険? 1市販の電気柵は安全対策が施されている 2死亡事故が起こったのは自作の電気柵 4電気柵の安全を確保する法律 5市販の電気柵の魅力 1心理柵としての効果が期待できる 2費用対効果が高い 3資格不要で設置が簡単 6電気柵による感電事故を防ぐための対策 1電気柵を設置した付近に看板を置く 2条件に適合する電源装置を使用する 3漏電遮断器を設置する 7家庭用電源を使用する際の注意点 8電気柵に使用する電源の種類 1乾電池タイプ 2バッテリータイプ 3ソーラータイプ 4ACアダプタータイプ 9電気柵の選び方 10まとめ|市販の電気柵は安全対策が行われているため事故が起きにくい 電気柵による事故の事例:静岡県西伊豆町 2015年、静岡県西伊豆町で電気柵がかかわる事故が発生しています。川で遊んでいた子どもが、土手のアジサイ畑周辺に設置されていた電気柵に触れて感電してしまったという事故です。感電した1人の子どもを助けようとしたほか6人も次々と感電し、7人が病院へ搬送され、そのうち2人が亡くなる重大な事故になってしまいました。 電気柵は、近隣の男性がアジサイの花壇をシカから守るために設置したものでした。市販の電気柵ではなく自作の電気柵を設置しており、農機具小屋の家庭用コンセントを使用していて、漏電遮断器の設置がなかったとみられています。 電気柵の役割とは 電気柵は、大切に育てた畑を害獣から守る役割があります。畑の周囲に設置すると、イノシシやシカなどの獣がエサを求めて畑に侵入し、荒らしてしまうのを防いでくれます。電気柵の電線にはプラスの電気が、地面にはマイナスの電気が流れており、動物が電線に触れると回路が通じ、電線から動物の体をとおって地面に電気が流れます。これが感電の仕組みです。 害獣が柵に触れると電気が流れるため、痛みや衝撃に驚いて逃げていきます。電気柵に触れると感電する仕組みを覚えさせて、近寄らなくなるようにする効果があります。なお、電線に虫が止まっても感電しないのは、電気の流れる回路が通じないためです。電気柵は、対象が電線と地面の両方に触れている状態で効果を発揮します。 電気柵は安全?危険? 電気柵は、動物が電線に触れると電気が流れる仕組みですが、人間が触れてしまったときに大けがをしてしまうのではないかと心配を抱えている人もいるでしょう。市販の電気柵には安全に利用できる工夫がされており、人間が誤って触れてしまってもけがをしないようになっています。ビリッと強い衝撃は受けますが、通常大けがにはいたりません。ここでは電気柵の安全性について具体的に解説します。 市販の電気柵は安全対策が施されている 市販の電気柵は、柵自体の電気の力である電圧は高くとも、電気が流れる力である電流は弱い製品が多いため、人を含めた生き物を傷つける心配はありません。また、電気が身体に流れるのもごく一瞬です。 市販の電気柵は、常時電気が流れているのではなく、約1秒間隔で瞬間的に電気を流すパルス出力形式と呼ばれる仕組みが作られています。そのため、誤って触れて電気が流れてしまっても、すぐに手を離すことが可能です。触れてしまったときにビリビリと電気が流れ続けるのではなく、ドアノブに触れて静電気が発生したときのようなイメージを持つと良いでしょう。 また、市販の電気柵は、電気事業法やそれに関する省令にもとづいて安全性を確保したうえで製造されています。必ず安全装置を設置することになっているため、安心して利用できるといえるでしょう。 死亡事故が起こったのは自作の電気柵 西伊豆で起きた死亡事故で設置されていた電気柵は、市販製品ではなく自作のものでした。そのため、電気を断続的に一瞬だけ流す安全装置が整備されておらず、死亡事故につながってしまったと考えられます。なお、これまで市販の電気柵による死亡や重傷事故は起きていません。 畑や花壇を害獣から守るために電気柵は重要な役割を果たします。なかには、設置費用を抑えるために電気柵を手作りする人もいるでしょう。しかし、電気柵を自作する際は、安全に利用できるかのチェックが欠かせません。必ず安全装置を設置して、事故につながらない仕組みを作る必要があります。 電気柵の安全を確保する法律...