しかし、電気柵を設置しても害獣による農作物の被害が減らずに困っている人もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では電気柵の仕組みを解説するとともに、害獣対策に効果的な電気柵の設置方法や選び方も紹介します。
害獣による被害を出さないために、まずは電気柵の仕組みをしっかりと理解しましょう。
目次
そもそも電気柵とは?

ここでは電気柵の基本情報を解説します。はじめて電気柵を使用する人のなかには電気柵に関する前提知識がなく、手探りで導入を進めている人もいるでしょう。
電気柵の主な用途や構成要素といった基本情報を紹介しますので、効果的な電気柵の導入にぜひ役立ててください。
電気柵の主な用途
日本における電気柵の主な用途は、害獣対策と家畜管理の2つです。イノシシ・シカ・ハクビシン・アライグマなど、農作物を狙う害獣から畑を守るために使用したり、牛・馬・羊などの家畜が管轄エリアの外に出ないようにするために使用したりします。一方で、海外では野生動物を保護する用途や、住宅への不法侵入に対する防犯対策の用途で電気柵を使用する場合もあります。例えば、ウガンダでは、野生動物の保護区域周辺に電気柵を設置し、住宅地域や農耕地への侵入防止に役立てられています。
ただし、日本では害獣対策や家畜の管理以外の用途で電気柵を使用することは禁止されているため注意しましょう。不適切な使用は安全上の問題を引き起こすだけでなく、動物へ不必要な危害を加えることにもなりかねません。適切な管理と運用を心がけましょう。
電気柵の構成要素
電気柵は電線や支柱、アースなどのパーツで構成されています。主な電気柵のパーツと用途は以下のとおりです。|
パーツ |
用途 |
|
・電気柵を動かすための動力源 ・設置場所や環境に応じて乾電池やバッテリー、家庭用AC電源などが使用される |
|
|
・動物が触れると電気ショックが流れる線のこと ・主にナイロンコードにステンレス線を編み込んだものやアルミ製のものなどが使用される |
|
|
・導電線を支えるための柱のこと ・一般的に、ビニールなどの樹脂で覆われた金属製の支柱や絶縁性のあるプラスチック製の支柱が使用される |
|
|
・本体と接続して地面に埋め込む金属製の棒のこと |
|
|
・電気を発生させる電源装置のこと |
|
|
・電線を支柱に固定するための部品のこと ・電線から支柱を通って漏電しないよう絶縁性のものが使われる |
メーカーごとに多少仕様の違いはありますが、基本的な構成要素は同じです。最近ではホームセンターやAmazon・楽天などのECサイトでも気軽に電気柵を購入できます。
以下の記事では、電気柵に必要な資材や部品を詳しく解説しています。電気柵の導入を検討している人はぜひ参考にしてみてください。
電気柵に必要な部品って?
電気柵の種類と特徴
電気柵には、乾電池式・バッテリー式・ソーラー式・AC電源式の4種類があります。それぞれ特徴に違いがあるので、設置場所や目的にあわせて選ぶことが重要です。乾電池式は、単1電池や単2電池などで稼働する電気柵のことを指します。導入コストが低いうえ、どこにでも手軽に設置できることが特徴です。
ただし、電池切れを頻繁に確認する手間と、乾電池を交換するための維持費がかかる点に注意しましょう。
バッテリー式は、本体内蔵のバッテリーや外部バッテリー(自動車バッテリー)で稼働する電気柵です。1回の充電で乾電池式よりも長時間稼働できるうえ、充電すれば繰り返し使えるのでランニングコストを抑えられます。
ただし、乾電池式と同じようにバッテリー切れには注意が必要です。1回の充電で本体が稼働できる時間を確認して使用しましょう。
ソーラー式は、太陽光を利用した電気柵です。電気代がかからないうえ、電源を確保する必要がなく、設置場所が限定されにくいことが魅力といえます。
ただし、日当たりが悪い場所に設置すると電力が低下するおそれがあるため、バッテリーや乾電池と併用できるタイプを選ぶのがおすすめです。
AC電源式は、コンセントで電源を確保するタイプの電気柵です。家庭用電源から給電できるので、電気が切れる心配が少ないといえます。
ただし、設置できる距離がコンセントの長さに依存する点や、電気代がかかる点には留意しておく必要があります。
電気柵の仕組み

電気柵の電線に動物が触れると、電流(パルス電流)が動物の体を経由して地面(地中に設置したアース)に流れ、電気の回路が完成する仕組みになっています。
電流が流れるのは一瞬なので、電気柵に触れても人間や動物に危害が加わる可能性は低いものの、動物に恐怖心を抱かせるには十分な電気ショックが発生します。
電気柵の仕組みを理解するうえで重要なのは、電気ショックが発生するために電気柵と地面の両方に動物が触れている必要があることです。
プラスの電極である電気柵とマイナスの電極である地面(地中に設置したアース)に動物が同時に触れていないと電気ショックが発生しないためです。
電気柵の効果を十分に発揮するためには、地面の乾燥や電気柵の接地不良がないように設置する必要があります。
電気柵の効果的な設置方法

ここでは電気柵の効果的な設置方法を解説します。せっかく電気柵を使用しても、設置方法が誤っていると十分な効果が得られません。
これから電気柵を設置する人はもちろん、すでに電気柵を設置している人も、電気柵の正しい設置方法を改めて確認しましょう。
必要な道具を用意する
まずは、電気柵の設置に必要な以下の道具を用意してください。・本体
・支柱
・碍子(ガイシ)
・簡易緊張具
・ゲートクリップ
・電線
・アース
・本体設置杭
・危険表示板
・検電器
このように電気柵を設置する際は、多くの部品や道具が必要になります。必要なものを選ぶ作業は非常に手間がかかるため、セット商品を購入するのがおすすめです。
セット商品には基本的に必要な道具がすべて含まれているので、電気柵の設置がはじめての人でも安心して使用できるでしょう。
ほかにも設置作業には支柱を打ち込むためのハンマーや、電線を切るためのハサミ・ニッパー・軍手なども準備しておくとよいでしょう。また、支柱を打ち込むときはゴムまたはプラスチック製のハンマーを使用すると、支柱が傷つくリスクを軽減できます。
設置の準備をする
必要な道具が揃ったあとは、電気柵の設置場所を整備しましょう。設置場所の周辺に生えている雑草を刈り、地面を平らにして支柱を立てやすくします。雑草を取り除くのは、電気柵に雑草や木の枝が触れて漏電することを防ぐためです。
また、動物が隠れる場所を減らして農地への接近を防ぐためにも、草刈りは効果的といえます。
なお、支柱や柵を設置するときの間隔は、対象の動物に応じて調整することがポイントです。
動物の体毛に覆われている部分は電気ショックが流れにくいため、電気ショックの流れやすい鼻先に電気柵の高さをあわせることが狙いです。
例えば、イノシシの場合は支柱間隔を4m以内、柵の間隔を20cmで2段または3段に調整するとよいでしょう。
ハクビシンの場合は支柱間隔を4m以内、柵の間隔を10cmで4段に調整するのがおすすめです。
支柱と柵を設置する
設置場所の準備が整ったあとは、支柱と柵を設置していきます。まずは、支柱を地面に20〜30cmの深さまで打ち込みます。電気柵を四角形のエリアに設置する場合、四隅と出入口の6か所に打ち込んでください。支柱を設置したあと、地面に最も近い部分からワイヤーの取り付けを開始します。出入口から支柱の外側へワイヤーを張りましょう。
次に支柱の上から、動物の種類に応じた適切な高さでワイヤーを固定します。このとき碍子を使わず直接支柱にワイヤーを固定すると、あとからワイヤーを回収したり、調整したりすることが難しくなるため、注意してください。
ゲートクリップを取り付けるときは、出入口のワイヤーにゲートクリップを連結し、フックは出入口の碍子に掛けてください。
最後に、ワイヤーの締め付け具合や高さの調整がしやすいように、簡易緊張具をワイヤーに掛けます。
本体とアースを設置する
支柱と柵の準備が完了したら、電気柵へ電気を供給するために本体とアースを設置していきます。まずは本体設置杭を地面に打ち込み、杭に電気柵の本体を固定しましょう。本体は地面に触れない位置に設置します。ソーラー式の場合、日光を受けやすい方向にソーラーパネルを向けてください。
アースは湿り気のある地中深くに埋め込みます。アース全体が地面に埋まるよう垂直に埋め込みましょう。
乾燥した土壌やアスファルトの近くは通電性が悪く、電気柵の効果が十分に得られない場合があるので注意が必要です。
また、複数のアースを設置する際は、できるだけ間隔を空けて埋め込むことが重要です。最後にアース・本体・電気柵を端子で接続すれば設置は完了です。
電気柵の設置が完了したら、目立つ場所に危険表示板を必ず設置しましょう。
電圧テストを行う
アースや本体の設置が完了したら検電器を使用し、最低でも4,000V以上の電圧があることを確認します。このとき、1か所だけではなく複数か所の電圧をチェックし、電気柵全体に通電していることを確認するのがポイントです。電圧が低い場合は周囲を点検し、雑草や木の枝などの接触物を取り除いて再度チェックしてください。問題がなければ電気柵を稼働させましょう。
なお、電圧が低くなっている部分を特定する方法としては、電気柵を2~3区画に区切って確認する方法がおすすめです。例えば、周囲が600mの場合、200mごとに電気柵の電線を区切り、各区画それぞれの電圧を測定します。漏電している区画が特定できたら、さらにその半分の100mに区切って測定しましょう。
これを繰り返すことで電圧が低くなっている原因が特定しやすくなります。
以下の記事でも電気柵の設置方法や害獣対策のポイントと注意点を詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
電気柵の設置方法とは?害獣対策のポイントと注意点をご紹介
電気柵を安全に使用する方法

ここでは電気柵を安全に使用する方法を解説しています。電気柵を設置する際は、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)に則って設置しなければなりません。
安全性に関わる部分であるため、忘れずにチェックしましょう。
漏電遮断器を設置する
人が立ち入る場所に30ボルト以上の電源から電気柵に電気を供給する場合、漏電による危険防止のため、以下に適合する漏電遮断器を設置することが義務付けられています。・電流動作型のものであること
・定格感度電流が15mA(ミリアンペア)以下かつ、動作する時間が0.1秒以下のものであること
また、蓄電池や太陽電池などから電気を供給する場合でも、漏電遮断器を設置する必要があります。過去には漏電遮断器を設置していなかったことで死傷事故に繋がったケースもあるため、必ず設置しましょう。
電気柵専用の本器を使用する
電気柵には、電気用品安全法の適用を受けた電気柵専用の本器(電源装置)を使用する必要があります。具体的には、電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置を使用しなければなりません。蓄電池や太陽電池などを使用する場合も直流電源である必要があります。
電気柵専用の本器は、通電時間と通電間隔を制御できるなど、安全性に配慮した処置が施されています。動物に必要以上の危害を加えないためにも、電気柵は自作せず専用のものを使用することが重要です。
開閉器を設置する
万が一事故が発生したときのために、簡単に電力を解放できる電気柵専用の開閉器を設置しなければなりません。加えて、電気を簡単にオン・オフできる位置に設置する必要があります。開閉器とは、電気柵専用の本器や漏電遮断器に付属しているスイッチのことを指します。電源装置本体に開閉器が付属されていてスイッチが容易に操作できる場合は、外部に追加する必要はありません。
危険表示板を設置する
危険表示板は、人が見やすい位置に適当な間隔をあけて設置することが法律で定められています。人や動物に危害が加わる可能性が低い装置とはいえ、電気柵を設置した場所には必ず危険を知らせる表示板を設置してください。また、危険表示板を設置したあとも雑草や木などで危険表示板が隠れないように日々の点検は欠かさず行いましょう。
なお、危険表示板は1枚単位であれば数百円、5〜10枚セットであれば数千円で購入できます。まだ用意ができていない人でもECサイトで手軽に購入できるでしょう。
電気柵の選び方

ここでは電気柵を選ぶときのポイントを紹介します。電気柵は設置する場所や対策したい害獣に応じて選ぶことが重要です。適切な電気柵を選んで効果的に害獣対策をしましょう。
土地の広さにあわせて選ぶ
電気柵を設置する際は田畑の外周にあわせた電線が必要です。設置場所の正確な外周長を測定し、土地の広さにあった電気柵を選びましょう。電気柵には推奨延長距離と呼ばれる、漏電抵抗を考慮した使用可能距離の目安が記載されています。電気柵を選ぶときは、土地の広さよりも推奨延長距離が長いものを選ぶのがポイントです。このとき、土地の広さに加えて、電線の段数も考慮しましょう。例えば、500mの電線を2段設置する場合や250mの電線を4段設置する場合は、推奨延長距離が1,000mのものを選んでください。
また、動物が侵入しやすい段差がある場所には、支柱の立て方や配線方法に工夫が必要な場合もあるので注意が必要です。
設置場所と使用時間にあわせて選ぶ
電気柵の種類は、乾電池式・バッテリー式・ソーラー式・AC電源式のなかから、設置場所と使用時間にあわせて選びましょう。例えば、電源の確保が難しい場所で夜間のみ稼働する場合は、乾電池式やバッテリー式が適しているでしょう。一方で、電源の確保が難しい場所で1日中電気柵を稼働し続けたい場合は、バッテリー式・乾電池式にソーラー式を組み合わせたものやAC電源式がおすすめです。
電気柵は種類によってそれぞれ特徴が異なるため、設置予定の場所と電気柵を使用する時間に応じて選ぶことが重要です。
対策したい害獣の種類にあわせて選ぶ
電気柵の電線の段数は害獣のサイズや特性にあわせて選びましょう。例えば、一般的にイノシシは2段、シカやハクビシンは4段の段数になっている電気柵が推奨されています。電気が通りやすい動物の鼻先に柵線がくるよう高さを調整する必要があるためです。また、動物が電気柵の下に潜り込むこともあるため、その点を考慮して電線の段数を選びましょう。
なお、段数が多くなると必要な電線の長さや碍子の数も増加します。段数の多い電気柵を選ぶ場合は、必要な資材がすべてセットになっている商品を選ぶとよいでしょう。
以下の記事では、はじめて電気柵を買う人はもちろん、電気柵を買い換えようと思っている人にも役立つ電気柵の選び方を詳しく解説しています。具体的なおすすめの商品も紹介しているので、電気柵選びに悩んでいる人はぜひチェックしてみてください。
電気柵の選び方とおすすめ商品12選を紹介!害獣の見分け方もあわせて解説
まとめ|電気柵の仕組みを理解して、効果的に害獣対策しよう

農地や家畜の保護から野生動物の安全確保まで幅広く利用されている電気柵ですが、効果的な設置や安全性に配慮した使用のためには、電気柵の仕組みを理解することが重要です。また、仕組みを理解したうえで電気柵の設置方法や選び方も網羅的に理解することが、効果的な害獣対策に繋がります。
イノホイでは、鳥獣対策に便利な幅広い商品をラインナップしています。ほかにも農業に役立つ情報を多数掲載しているので、ぜひご活用ください。
https://inohoi.com/
ソーラー式電気柵 おすすめ商品
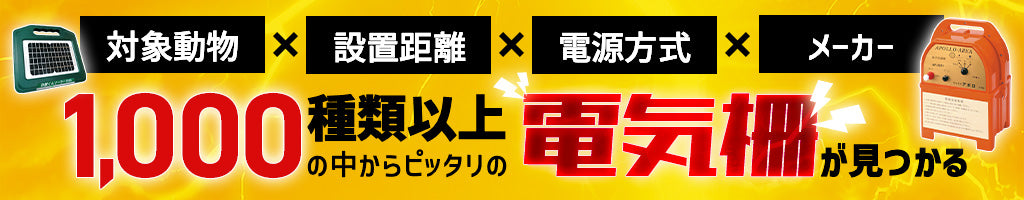

 箱罠
箱罠
 くくり罠
くくり罠
 パーツ類
パーツ類
 電気柵
電気柵
 自作キット
自作キット
 防獣グッズ
防獣グッズ
 監視カメラ
監視カメラ

 電気柵 防獣くんソーラー600 お手軽 100mセット(2段張) ネクストアグリ
電気柵 防獣くんソーラー600 お手軽 100mセット(2段張) ネクストアグリ  電気柵 防獣くんソーラー1500 お手軽 100mセット(2段張) ネクストアグリ
電気柵 防獣くんソーラー1500 お手軽 100mセット(2段張) ネクストアグリ  アポロ電気柵 AP-2011-SR 200m×2段(イノシシ用)本体+部材セット ソーラー
アポロ電気柵 AP-2011-SR 200m×2段(イノシシ用)本体+部材セット ソーラー 


 箱罠
箱罠
 くくり罠
くくり罠
 囲い罠
囲い罠
 防除・忌避グッズ
防除・忌避グッズ
 電気柵
電気柵
 罠監視用カメラ
罠監視用カメラ
 運搬グッズ
運搬グッズ
 罠作動検知センサー
罠作動検知センサー
 狩猟お役立ち品
狩猟お役立ち品
 狩猟関連書籍
狩猟関連書籍
 防鳥グッズ
防鳥グッズ
 農業資材・機械
農業資材・機械
 イノシシ
イノシシ
 シカ
シカ
 キョン
キョン
 サル
サル
 アライグマ
アライグマ
 アナグマ
アナグマ
 ハクビシン
ハクビシン
 タヌキ
タヌキ
 ヌートリア
ヌートリア
 ネズミ
ネズミ
 モグラ
モグラ
 クマ
クマ
 ハト
ハト
 カラス
カラス







