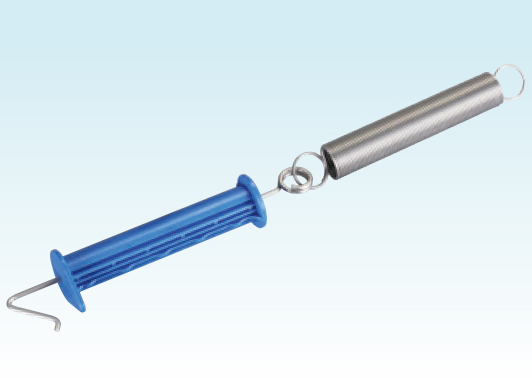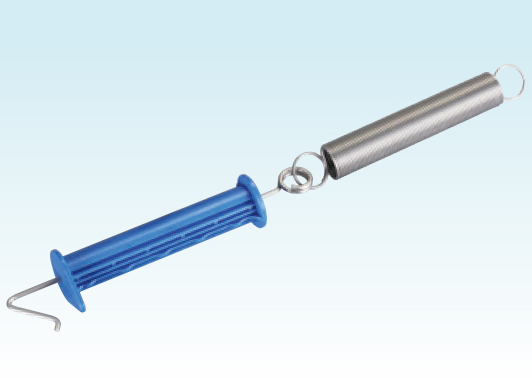目次 1止めさしの前に 2止めさしの種類 1銃器を使用する方法 2ナイフや槍といった刃物を使用する方法 3電流で感電させる方法 4炭酸ガスなどを用いた化学的な処理 3まとめ ※注意:この記事は、狩猟や鳥獣被害に理解のある方のみ閲覧ください。いわゆる動物愛護観点からのコメントには応じかねます。 近年、鳥獣被害対策として箱罠やくくり罠、囲い罠等を用いて、イノシシやシカ等を捕獲する取り組みが広がってきています。 それに伴い、捕獲するまでのノウハウや、食肉活用についての事例紹介は多く目にするようになりましたが、実際に獣が罠にかかった場合、どのような処理が必要となるかについては、あまり議論が多くないように感じます。 野生獣は想像以上に身体能力が高く(特にイノシシ)、捕獲した獣は生死がかかっているので、予想外の動きを取ることもあります。例えば、くくり罠において足をくくっているワイヤーが獣が動いた拍子に外れ、逆襲されたことによる死亡事故も発生しています。 この記事では、捕獲した獣にできる限り苦痛を与えず、安全かつ速やかに「止めさし」を行う技術について、説明いたします。 止めさしの前に まずは、獣が罠にかかっている現場の状況をしっかりと確認することが重要です。イノシシの捕獲では、わなの見回りや捕獲個体の止めさしの際に、最も事故が発生する確率が高くなります。 いきなり近づいて確認せずに、まずは遠くから双眼鏡などを用いてチェックするのがベストです。遠くからゆっくりと近づき、傾斜のある場合は高いほうから徐々に近づくことが基本です。 くくり罠の場合は、以下がチェックポイントになります。 ▶ワイヤーが獣のどの部位を括っているか ▶括った箇所が抜けかかっていたり、切れかけたりしていないか ▶括った部分の体の部位が、ちぎれかけていないか ▶支点にしている部分からワイヤーが抜けたりしないか ▶獣の可動範囲はどの程度か 箱罠の場合は、以下がチェックポイントになります。 ▶箱罠に破損はないか ▶獣が逃げ出す恐れはないか(扉やストッパーの確認) 離れた場所から、手をたたいたり、大きな声を出して、捕獲された獣の反応を観察するとともに、捕獲された個体の近くに他の個体が潜んでいないかも確認しましょう。 止めさしの種類 止め刺しの種類としては、大きく分けて4つあります。 >1. 銃器を使用する方法 最も威力が大きい方法です。基本的には一発弾のスラッグ弾を使用します。威力の高いプレチャージ式の空気銃が使用されることもあります。使用する銃器に応じて、「第一種銃猟」または「第二種銃猟」の免許と、「銃所持」の許可が必要です。 離れたところからでも止めをさすことができることや、大型の個体でも安全に対処できることがメリットです。 銃器を止めさしに使用する場合、注意すること まず、銃猟禁止区域など、銃が使用できない場所があるため、そのような場所に該当しないことを事前にチェックしておきましょう。 また、矢先に民家や人がいないか必ず確認し、バックストップ(弾が範囲を越えて行かない為の遮蔽物)をきちんと確保しましょう。 跳弾にはくれぐれも注意する必要があります。発砲の際は、銃所持者以外は銃所持者の後ろ側に立ち、できるだけ木などの陰に隠れるようにしましょう。 参考動画:80キロオーバー!大物イノシシ猟スラッグ弾止めさし シカの場合は、頭部か首、心臓を狙います。またイノシシの場合は、眉間、こめかみ(耳のうしろ)、心臓を狙います。 しかしながら、心臓を的にした場合、損傷が大きかったり、弾の破片が肉に入り込んだりするため、食肉活用が難しくなる場合があります。...