鳩は古くから私たちの身近に存在する鳥であり、都市でも自然の中でもさまざまな姿を見かけます。彼らは穏やかな印象を持たれがちですが、実は多彩な行動パターンや強い帰巣本能など興味深い特徴を持っています。
本記事では、鳩の種類や食性、繁殖サイクルから人間との関わり方まで、鳩にまつわる知識を幅広くご紹介します。彼らの生態を理解することで、共存に向けた正しい対策や鳩との上手な付き合い方が見えてくるでしょう。
都市の公園やビルの隙間などあらゆる場所で目にする鳩ですが、その行動様式は単純なようで実は奥が深いといえます。彼らの生活圏や繁殖パターンを知ることは、正しく対策を講じるうえでも重要です。
目次
鳩とはどんな鳥?基本的な生態と特徴
まずは鳩という鳥がどのような生き物なのか、形態的・行動的な基本の特徴を押さえておきましょう。
鳩は世界中に広く分布し、都市から山間部までさまざまな環境下で生活しています。近年では都市部に適応しており、人間が出す食べ物の残りや、ビルの隙間などを積極的に利用している点が特徴です。物陰や高所を使って休むため、身近にいても意外に見落とされがちな一面もあります。
体長はおよそ30cm前後で、種類によって羽色や模様が異なります。一般的に鳩は雑食性で、木の実や種子、農作物のほか、人間の食べ残しなどを食すことも多いです。都市部においてはエサ場やねぐらが確保されることで、野外生物としては異例の高い繁殖力を維持できるといわれています。
また、鳩は集団行動をとる傾向が強く、一度暮らしやすい場所を見つけると大規模な群れを形成します。この群れが定着するとフン被害などが問題化しやすくなるため、基本的な生態を理解し、早めの対策が必要になることも覚えておきましょう。
代表的な鳩の種類:ドバト(カワラバト)とキジバト
日本でよく見られる2種類の鳩、それぞれの特徴や生活環境を把握することで、鳩への理解を深められます。
日本で最も多く見かけるのはドバト(カワラバト)とキジバトです。両者とも人里に近い場所で生活しますが、活動範囲や群れの規模、好むねぐらには微妙な違いがあります。正しく見分けることで、効果的な対策や観察がしやすくなるでしょう。
ドバトは市街地を中心としたエサ場を求めて大規模な群れを作る一方、キジバトはやや郊外や農耕地帯に多いといわれています。どちらも穀物や種子を好む点や、1年を通して繰り返し繁殖を行う点は共通しています。都市化が進むにつれ、キジバトも街中で見られる機会が増えているのが近年の傾向です。
両者の生態や分布を知っておくと、マンションや戸建てのベランダ、屋根裏、橋桁などに巣を作るリスクの予測が立てやすくなります。特に大群で生活するドバトはフン被害や騒音の原因になりやすいため、個体数が増えやすい環境を放置しないことが大切です。
ドバト(カワラバト)の特徴と生活環境

ドバトは一般的に灰色の羽を持ち、首元に金属光沢のある模様がある個体も多く見られます。名前の由来は瓦屋根のある場所に定着したからといわれ、人間が生活するエリアでの適応力が非常に高いです。ビルの屋上や橋の下など、比較的狭い空間でも群れを作って暮らします。
食べ物については、本来は種子や穀物をメインとしながら、都市部ではパンくずなどの残飯も頻繁に食べます。そうした手軽なエサ源があるため、都市部のドバトは栄養バランスを比較的保ちやすく、年間を通じて複数回の繁殖が行えると考えられています。一度住み着くと追い出しが難しくなるのも特徴の一つです。
また、ドバトは大量に集団を形成するため、フンや羽毛被害が社会問題化することがあります。定着が進む前の段階でネットや突起物(スパイク)などを活用し、ねぐらを作らせない対策が有効だとされています。
キジバトの特徴と生活環境

キジバトは全体的に茶色みのある羽を持ち、翼にはうろこ状の模様が見られるのが特徴です。山間部や農耕地帯を好む種ですが、近年では住宅街の生垣や公園の植え込みなどでもしばしば姿を見かけるようになりました。鳴き声が「デデッポー」と独特なリズムを刻むため、聞き覚えのある人も多いでしょう。
ドバトよりも単独または小規模な群れで行動する傾向があるため、都市部ですれ違っても大量発生といった印象は少ないかもしれません。しかし、活動エリアを選ばずに移動する性質もあるため、ベランダや軒下でも巣を作る可能性があります。周囲に植物があれば、エサとなる種子や果実を得る機会も多いです。
キジバトは警戒心が比較的強く、人通りの多い場所にはあまり近づかないといわれています。ただし、エサや休める場所が確保されると環境に馴染んでしまうため、被害対策の面では早めに対処することが望ましいでしょう。
鳩の食性:食べ物の種類と栄養源
鳩は雑食性ですが、主に穀物や種子を好みます。都市部では人間の食べ物の残りも大きな栄養源となっています。
鳩の主なエサは穀物や種子で、トウモロコシやヒマワリの種など多様な植物を食べています。人間が落としたパンやお菓子のくずなども好んで食べるため、市街地では手軽な食料に恵まれることが多いのが現状です。エサ場に多くの鳩が集まると、繁殖力がさらに高まる要因にもなります。
栄養バランスとしては、縄張り内で拾える種子や穀物から必要なタンパク質や脂質を補給しています。水分補給の際には多くの鳥と異なり、くちばしを水に浸して吸い込むように飲めるという特徴的なスタイルをもっています。こうした摂食・飲水スタイルのおかげで、地面にある水たまりなどでも簡単に水分を得ることが可能です。
都市部では栄養過多になりやすいという指摘もあり、フンの量が増えて公衆衛生面で問題になることもあります。不要な被害を防ぐには、むやみに鳩にエサを与えず、生息環境を最適化しないことが肝心です。
鳩の天敵と生存戦略
都市部でも自然環境でも、鳩にはカラスや猛禽類などの天敵が存在します。鳩がどのように生き残るかを見ていきましょう。
鳩にとって自然界の天敵にはカラスやタカ、ノスリなどの猛禽類が挙げられます。これらの捕食者が比較的少ない都市部は、鳩にとって安全が確保しやすい環境といえるでしょう。ただし、カラスも都市に多いため、巣やヒナが襲われるケースも皆無ではありません。
また、ネコなど小型の哺乳類も天敵となる場合がありますが、鳩が高所や狭い隙間を好んでねぐらや巣にするため捕まえにくい面があります。群れで行動することで、警戒心をはたらかせやすくなる点も生存戦略の一部といえるでしょう。人間による駆除や対策も含め、都市環境ではさまざまな要素が鳩の生存を脅かす可能性があります。
ただし、鳩は適応力が高いため、多少のプレッシャーでは生息数が大きく減ることは珍しいです。エサ場の確保や繁殖回数の多さが、結果的に天敵からのリスクを上回り続けていると推察できます。
鳩の繁殖サイクルと巣作り行動
多くの種類が一年を通じて繁殖活動を行います。巣作りや産卵・ヒナの成長、帰巣本能までを詳しく解説します。
鳩の多くは繁殖期に明確な区切りを持たず、条件が整えば一年中産卵を続けることができます。都市環境では暖かい建物の隙間や豊富なエサがあるため、季節を問わずに繁殖を繰り返すことが可能です。巣は小枝や枯れ葉を適当につなぎ合わせた簡素なつくりで、ビルの軒下やベランダの屋根部分など場所を問わず作られます。
一度巣を作り始めると、巣立ち後も同じ場所を使い続けることが多く、フンや羽などの汚れが積み重なります。被害を防ぐには、巣作りの兆候を早めに察知して撤去や対策を施すことが効果的です。また、鳥獣保護法に関わる場合もあるため、法的な手続きを確認する必要があります。
鳩の強い帰巣本能によって、巣を排除しても同じエリアに戻ってくる場合があるのが厄介な点です。根本的な対策としては、安易に巣が作れない環境整備や、物理的なバリア設置を考える必要があるでしょう。
産卵・抱卵の流れと雛の成長

鳩は通常、1度の産卵で2個の卵を生み出し、親鳥が交代で約2週間ほど抱卵を行います。卵は比較的短い期間で孵化するため、都市部では一つの巣で年に何度もヒナが孵ることもしばしばあります。ドバトやキジバトともに繁殖力が強いため、個体数がなかなか減少しにくい背景があります。
孵化したヒナは“ピジョンミルク”と呼ばれる親鳥の作り出す液状の餌を与えられます。これによってヒナは急速に成長し、およそ1か月ほどで巣立ちを迎えます。人目に触れることが少ないため、実際に巣立つ直前のヒナを見る機会はあまり多くありません。
巣立ち後も一定期間は親鳥の近くで過ごし、飛行や餌の取り方を学んでいきます。鳩の早い繁殖サイクルが、都市部での数の増加につながることを改めて意識しておくとよいでしょう。
帰巣本能がもたらす鳩の行動パターン
鳩は非常に強い帰巣本能をもち、遠くへ飛んだ場合でも元の巣やねぐらに戻ってくる性質があります。人類はこれを活かし、メッセージを運搬する伝書鳩として古くから利用してきました。現在では通信手段が発達していますが、伝書鳩の歴史は鳩の帰巣本能の顕著な実例といえます。
この帰巣本能は、鳩が環境の変化に強い適応力を発揮する一因となっています。巣や餌場が破壊されても、同じエリアを再び訪れ、適した場所を見つけて再度根付きやすいのです。都市部での被害が長引きやすいのは、こうした執着の強さにも理由があります。
被害対策を成功させるためには、この帰巣本能を考慮して物理的に立ち入りを制限することが重要です。同時に、餌となるゴミや残飯を管理し、鳩が居つかない環境を作ることが最終的な解決策につながります。
鳩の生活リズム:活動時間と休息の特徴
昼行性である鳩は、日中に餌を探し、夜間は決まった場所で休むというリズムを持ちます。
鳩は基本的に朝早くから活動を開始し、日中は餌場や水場を巡回しながら休憩を挟みつつ過ごします。それぞれの群れが数メートルから数十メートルの範囲を移動し、日が傾く頃にはねぐらとなる場所へ戻るのが一般的です。鳩独特の動きとして、足元を引きずるように小走りで移動する姿が見られます。
夜間は暗い中での視力があまり強くないため、高所や奥まったスペースをねぐらにして休息を取ります。群れ全体が同じ場所に集まる習性があるため、大量のフンや鳴き声で周辺に影響を及ぼすことが少なくありません。特にビルやマンションの屋上、看板の裏などは鳩にとって安全な隠れ家になりやすいです。
このような生活リズムを考慮すると、朝晩の出入りを制限する対策や、夜間の明るさを調整して近寄りづらくする方法なども有効です。休息の場所を人為的に不快な環境にすれば、別の安全なねぐらを探す可能性が高まります。
鳩と人間の関係:文化・伝書鳩・食用など
古くから鳩はさまざまな形で人間と関わってきました。伝書鳩や食用など、文化における鳩の立ち位置を見ていきます。
鳩は古代から平和の象徴や神聖な鳥として扱われることが多く、宗教的な儀式の場などにも登場します。また、強い帰巣本能を利用した伝書鳩の歴史は長く、交通手段や通信が未発達だった時代には、重要なメッセージ伝達手段として活躍してきました。これにより長距離を飛んで正確に戻る能力が広く知られるようになったのです。
一方で、食用としての歴史もあり、西洋や一部地域では鳩の肉を食べる習慣が存在します。日本ではあまり馴染みがありませんが、フレンチでは古くから「ピジョン料理」が有名でした。鳩の肉は低脂肪高タンパクな食材として重宝される場合もありますが、日本で流通するケースは限られています。
現代では鳩の大量発生やフン被害など、市街地での問題がクローズアップされる一方で、平和の象徴やアートのモチーフにもなっているのが鳩の不思議な魅力といえます。こうした文化的背景も踏まえつつ、人間との関係を冷静に捉え、適切に対処していく意識が求められます。
鳩の個体数管理と被害対策のポイント

増加傾向にある鳩の個体数をコントロールするため、物理的対策や環境整備などの方法を押さえておくことが重要です。
鳩を過剰に繁殖させないためには、まずエサ場を減らすことが基本的な対策となります。むやみにパンくずなどを与えれば、鳩はそのエリアに定着しやすくなり、フン害や鳴き声の問題につながりかねません。管理されていないゴミ出しも大きなイサカイの原因となるため、食物残渣を放置しないことが大切です。
鳩が好む高所や隙間を封鎖する物理的な手段も効果的です。屋根やベランダ、看板の裏などによく使われるのが防鳩ネットやスパイクで、巣作りを物理的に妨げることで被害を抑えます。頻繁に糞掃除を行い、清潔な環境を保つことも継続的な対策として大切です。
取り除いた巣や卵が鳥獣保護法の対象となるケースもあるため、法律を確認したうえで専門業者に相談するのが望ましい場合もあります。トラブルを未然に防ぐには、鳩の生態を把握したうえで適切な管理を行うことが最大のポイントといえるでしょう。
巣作り被害を防ぐための具体例と注意点
巣作り被害を防止するには、まず鳩が狙いやすい場所を特定し、早期に手を打つことが重要です。排水口やエアコンの室外機周辺などに巣の材料が集められ始めたら、速やかに取り除きましょう。巣が完成してしまうと、卵やヒナまで含めた撤去でより手間がかかるうえ、トラブルになりやすいです。
また、ベランダや屋根裏など人目につきにくい場所も定期的にチェックしておくとかかる費用や手間を抑えられます。巣作りを放置すると、フンによる衛生問題や建物へのダメージが大きくなる可能性もあるため、見逃さずに対策を実行することが大切です。
複数の箇所に巣を同時に作られることもあるため、問題を一つずつ解決するだけでなく、広範囲での見直しや清掃が必要です。特に高層ビルや大規模住宅の場合は、建物全体の対策を考えることでより効果的な被害抑制が期待できます。
利用できるグッズと環境整備の重要性

鳩対策としては、防鳥ネットやスパイク、超音波装置、鳥除け忌避剤など多彩なグッズが市販されています。ネットはベランダなど広範囲を覆うのに有効で、スパイクや金属ワイヤーはフェンスや手すりの上などに止まれないようにする目的で使われています。ただし、設置場所やバランスを誤ると効果が薄い場合もあります。
忌避剤は、ジェル状で塗布するタイプやスプレー式などがあり、鳩が不快感を抱いて近寄りにくくなる働きがあります。ただし、頻繁に塗り直しが必要だったり、季節や雨量によって効果が変動しやすい点に注意が必要です。併せて、巣材や食べ物の残りをこまめに掃除し、環境を整えておくことが重要となります。
環境整備ではゴミ管理も大きなカギになります。しっかりとフタ付きのゴミ箱を使う、食べ残しを放置しないといった基本的なルールを守るだけでも、鳩の寄り付き方は大きく変わります。グッズはあくまで補助的な手段であり、最終的には生活環境を見直すことが長期的な被害防止の鍵といえるでしょう。
まとめ・総括:鳩の生態を理解して快適に共生するために
鳩は身近な存在ですが、その生態や習性は多彩です。対策や正しい知識を持つことで、快適な共生を実現できます。
鳩の特徴を振り返ると、雑食性や高い繁殖力、そして強い帰巣本能など、都市環境との親和性が極めて高い鳥であることがわかります。そのため、一度定着すると個体数が増加しやすい一面がありますが、適切な対策を講じれば大規模な被害を予防・軽減できます。
代表的なドバトとキジバトの違いや、巣作りや産卵サイクル、天敵との関係などを知ることで、被害対策や共生への理解が深まります。被害を受ける前に高所や隙間をふさいだり、エサやりを控えたりすることは長期的にみて費用対効果が高い対策といえます。
鳩は歴史的にも人間の文化や生活に関わり続けてきました。適切な距離感を保ちながら、環境整備やグッズを上手に活用することで、これからも鳩と上手に付き合っていくことが可能となるでしょう。

 箱罠
箱罠
 くくり罠
くくり罠
 パーツ類
パーツ類
 電気柵
電気柵
 自作キット
自作キット
 防獣グッズ
防獣グッズ
 監視カメラ
監視カメラ


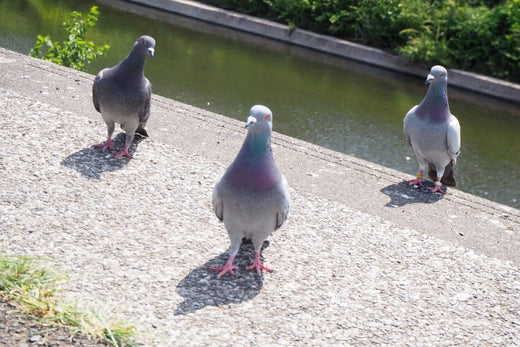





 箱罠
箱罠
 くくり罠
くくり罠
 囲い罠
囲い罠
 防除・忌避グッズ
防除・忌避グッズ
 電気柵
電気柵
 罠監視用カメラ
罠監視用カメラ
 運搬グッズ
運搬グッズ
 罠作動検知センサー
罠作動検知センサー
 狩猟お役立ち品
狩猟お役立ち品
 狩猟関連書籍
狩猟関連書籍
 防鳥グッズ
防鳥グッズ
 農業資材・機械
農業資材・機械
 イノシシ
イノシシ
 シカ
シカ
 キョン
キョン
 サル
サル
 アライグマ
アライグマ
 アナグマ
アナグマ
 ハクビシン
ハクビシン
 タヌキ
タヌキ
 ヌートリア
ヌートリア
 ネズミ
ネズミ
 モグラ
モグラ
 クマ
クマ
 ハト
ハト
 カラス
カラス







