イノシシやシカなど野生動物に田畑を荒らされることによる農作物の被害額は、全国で年間およそ200億円に上っている。そのため、農林水産省は山間部に近い自治体などに交付金を出し、動物が田畑に侵入するのを防ぐ「電気柵」等の柵を設置する補助事業を実施している。
この事業は、電気柵やワイヤを張った柵を田畑に設置するなどした場合、最大で全額が補助される「鳥獣被害防止総合対策交付金事業」。
事業の始まった2008年度から2017年度までの間、東京都を除く46道府県に約840億円が交付された。 この交付金による対策が適切に実施されているか、会計検査院が全国10余りの道府県を抽出して柵の設置状況を調べたところ、200か所以上で動物が容易に田畑に侵入できるような状態であることがわかった。
維持管理や設置方法に問題があったことが原因で、不具合によって計約5億円分の農作物被害が出ていた。 自治体が設置場所の地権者の合意を得ることができず、田畑を囲うように柵を設置できなかったケースや、柵が倒れて動物の侵入を防げない状態になっていたケース、さらに柵が倒れていた場所の中には、設置後1年以上点検していなかったケースもあったとのこと。
電気柵は、防護柵に通電することで、侵入しようとする野生動物に電気ショックを与え、物理的な遮断というよりは、心理的な遮断効果を狙うものである。適正に設置・管理できれば、高い効果が期待できるが、そもそも田畑を囲うことができないと意味がない。また設置後も、漏電防止などのメンテナンスが必要なこと、費用が割高であることがデメリットである。
今回の調査結果は、そもそも柵の設置時点で不備があったこと、設置後のメンテナンスが適正に行われていなかったことが浮き彫りになった形だ。会計検査院は、農林水産省に対し改善を求めることにしている。
参考記事:効果的な柵の設置方法について

 箱罠
箱罠
 くくり罠
くくり罠
 パーツ類
パーツ類
 電気柵
電気柵
 自作キット
自作キット
 防獣グッズ
防獣グッズ
 監視カメラ
監視カメラ


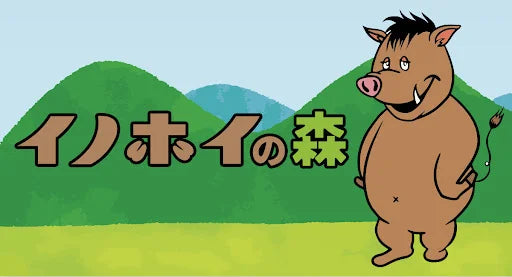






 箱罠
箱罠
 くくり罠
くくり罠
 囲い罠
囲い罠
 防除・忌避グッズ
防除・忌避グッズ
 電気柵
電気柵
 罠監視用カメラ
罠監視用カメラ
 運搬グッズ
運搬グッズ
 罠作動検知センサー
罠作動検知センサー
 狩猟お役立ち品
狩猟お役立ち品
 狩猟関連書籍
狩猟関連書籍
 防鳥グッズ
防鳥グッズ
 農業資材・機械
農業資材・機械
 イノシシ
イノシシ
 シカ
シカ
 キョン
キョン
 サル
サル
 アライグマ
アライグマ
 アナグマ
アナグマ
 ハクビシン
ハクビシン
 タヌキ
タヌキ
 ヌートリア
ヌートリア
 ネズミ
ネズミ
 モグラ
モグラ
 クマ
クマ
 ハト
ハト
 カラス
カラス







